5−11
日もすっかり落ちたころ、セルイが荷物を両手に抱えて帰ってきた。衣料が多いが、食料品も相当なものである。
自分ひとりではそんなに要らないんですけど、と前置きしてから彼は品物を並べ始めた。パンにチーズに干し肉…あとなにやらハーブのような草木類と種。砂糖菓子も混じっている。それを丈夫そうなガラス瓶に丁寧に詰めてゆき、パンは大きめの皮袋にしまった。イウギはその作業を興味深げに眺めていたが、やがて自分も手伝い始めた。
白い衣料が目立つ。包帯と曝しのようである。自分の包帯は取れているし、こんなに必要なんて彼はどこか怪我をしてるんじゃないかとイウギは訝しく思った。青年は相変わらずの調子で手際よく荷物を袋に詰め込んでいる。
一通り荷物が片付くと、青年はイウギのほうに向き直った。
「そうそう、お約束したものです。」
そう言ってにこやかに手渡されたものは、薄紫色の厚手の布にピンクのカタクリの花が刺繍された品のいい小袋だった。袋の口からは首にかけておけるぐらいの長さの紐がついている。イウギはまた胸がつかえて顔が赤くなるのを感じた。
「ありがとう…」
小さな声でつぶやくと、その小さな手芸に見入った。すると、青年がにわかに声を低くして言った。
「それと、これは私から…」
イウギが顔を上げると、彼はゆっくりと目の前に自分の短剣を差し出した。イウギが驚いて青年の顔を見返すと、彼はひどくまじめな顔をして、諭すような口調で続けて言った。
「これは守りの刀です。きっとあなたの事を守ってくれます。もらってください。あなた自身のために。」
言われてイウギは短剣をしげしげと見る。柄の部分は古びて輝きを失った黄金色だが、革づくりの鞘に納まったこの刀の刃は、何故かひどく穢れを知らない白銀のように思えた。
彼はこうも付け足した。
「崖で倒れていた貴方を救ったのも、実はこの剣なんですよ…?」
およそ、今の自分には必要のないもののように思われたが、少年はその刀を受け取った。セルイの言葉に、なにか真実めいたものを感じ取ったからかもしれない。
明日のことをいろいろと話し合ったあと、ふたりは床に就いた。イウギには気分が高揚として、眠れない夜となった。明日はいよいよこの街を発つ。自分が生まれ、育ってきたこの土地と別れるのだ。姉たちが、国を追われた時もこのような気持ちだったのだろうか。…いや、もっと絶望的な気持ちだったに違いない。自分には今、不安以上に勇力といっていいようなものも起こっているのだから。
翌朝、朝霧がおさまらぬうちに二人は街を出て街道に立っていた。イウギは新しい衣服を身にまとい、青年は新たに調達した荷物の袋を背負っている。
山際から朝日が差し込み、周囲(あたり)が一気に色彩を取り戻して行く。少年は、後方の山を振り仰いだ。
最後の生命を燃やし尽くし、散ってゆく紅葉が遠目にもはっきりと見えた。木々は生の時間を終息して死の時間へと入る。まもなくこの一帯は白一色に覆われるのだろう。少年は伏せ目がちに、その景色に背を向けた。
故郷をなくした最後の民は、ついにその地を離れたのである。
−−第1章 完−−
前へ 2章へ |
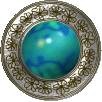 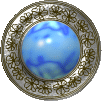 |